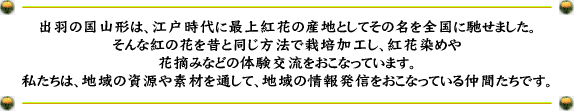「最上千駄」(もがみせんだ=馬千頭分=120kg×1000頭の「紅もち」生産)といわれ実に全国の半数以上であり、幕末の「諸国名産物番付」では、東の関脇に「最上紅花」が位置付けられています。
ところで、この紅花が、白鷹が置賜(山形県下)の主生産地であったことをご存じですか。
蒲生氏時代の文禄検地(文禄3年=1594年実施)を基に編纂されたとされている「邑鑑」(むらかがみ=上杉家文書)に、白鷹の各村(浅立、畔藤、石那田、馬場、十王、滝野、菖蒲、深山、高岡、蓑和田、鮎貝、山口、横越、高玉)で藩の御用作物として栽培されていることが記録されています。
これによると、紅花栽培の村は、置賜領内218村中35村あり、白鷹は22村中14村で栽培され、置賜最大の生産地でありました。
その後、広野、田尻、萩野、中山,大瀬、佐野原、下山、黒鴨、栃窪にも藩からの上納割り当てがあり、(万治3年=1660年頃)白鷹全村に及んだことがわかります。
また、青木家文書によると、正保3年(1646年)当時の紅花生産状況は、置賜領内の半数以上であったことが記録され、米沢藩の主要換金作物であった「青そ」同様荒砥の蔵に集荷されていたこと、畔藤村に花市場(水花)が開かれ賑わいを見せていたことなどが記録されています。
紅花(紅もち)は、米の100倍、金の10倍という貴重品でしたから、最上川舟運の難所「黒滝」開削後も危険箇所は、馬による陸送がなされました。
山形舟町、大石田、酒田と最上川を下り、日本海を北前船で敦賀に荷揚げされ、琵琶湖を経て、大津、京都と運ばれ、鮮やかな紅や衣装とされ、時の女性たちを魅了しました。(紅花は、1駄120kg単位=30キロ袋4つにしたが、その包み紙に、置賜領内では「深山和紙」が使用されています。)
このように、山形・白鷹と歴史文化的に深い関わりをもち、私たちの祖先が藩財政のために一生懸命栽培していた「紅花」を江戸時代同様に栽培加工し、地域づくりや交流観光など地域の活性化と美しいむらづくりなどに少しでもお役に立てればと願っています。
| 白鷹紅の花を咲かせる会 事務局長 今野正明 |